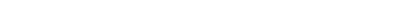60年目の夏に
前置
2005年春に亡くなった祖父の残した手記があります。
1945年8月6日8時15分。私の祖父は暗号兵として広島に居ました。
伝えていく事の出来る人はどんどん減ってゆきます。
サイトの主旨とは全く違ったものですが、せめてここに残したいと思い掲載しております。
以下は全て祖父の書いた文章です。
はじめに
この小文は、広島原爆五年後の一九五〇年に書き綴ったものですが、このたび、東京の季刊誌に掲載のため(一九八四年八月一五日発行)一部字句を手直ししてまとめたものです。
拙文ですが、私の体験をそのまま伝えたつもりです。少しでも、核兵器の恐ろしさと平和の尊さに思いを致して下さればと願っています。
爆撃のなかった広島
その日(昭和二十年八月六日)は雲一つない、しかもそよとも風の吹かない静かな天気だった。「ああ今日もまた暑いんだな」と思いながら、初年兵だった私は、朝七時ごろから公用自転車で宇品へでかけた。私は船舶部隊砲兵団(比治山)の暗号兵だったので、宇品の通信隊へ電信案文を三日おきくらいに持っていくのが、一つの仕事になっていたのである。
当時の広島は、比較的落ちついていた。いろいろな面での戦時中の窮屈さと乏しさは御他聞に洩れなかったが、どういうわけか、この広島には爆撃らしい爆撃はほとんどなかったといっていい。ただ、呉港爆撃のためと思われるB29が、ときたま上空を通過する程度だった。そのためか、市民も割合のんびりしていたように見受けられた。夕方など、ゆかた姿が比治山から眺められて、羨ましくてたまらなかったほどである。その時の広島は軍事基地にしては、意外に平穏だった。
爆裂一五分前に爆心地近くを通る
私は例の公用を済まして帰途についた。いつもなら、どこか人気のない場所を探して、とっておきのたばこ(兵隊は一日、金鵄四本だった)を思いきり喫いながら、自由の我にかえる。それが私にはささやかな安らぎの一瞬だった。だがその日は、なぜかそのまま兵舎に帰ってきたのである。私のいた兵舎は電報班だけのもので、人員は全部で二十人くらいの小さな掘立小屋程度のものだった。私はグッショリかいた汗を拭きながら、その兵舎の軒下に座って脚半を解きにかかった。まさにその時(午前八時一五分頃と記録されている)、あの世紀の爆発が起こったのである。
ボン! それは、鈍いしかし押しつめられた言いようもない強大な力が、突如、猛然とその外殻を突き破って爆発した、そんな音だった。瞬間、眼の中が、黄色に赤味を加えた閃光ででんぐりかえった。天空をバーッと覆った閃光だった。私は本能的にうつぶせに倒れた。とほとんど同時に、兵舎がガラガラと積み木細工を壊したように頭の上にかぶさってきた。ハッと我にかえった私は、必死で柱や棟木のすき間から這い出した。土埃をいっぱいかぶっていたが、奇跡的にかすり傷一つ負わなかった。兵舎のひさしの真下に一メートルくらいの堀代わりのちょっとした石垣があって、それが猛烈な勢いで倒れてくる柱や棟木を支えた格好となり、その下にすき間をつくってくれたのである。何が幸いになるかわからない。
幸いといえば、もし私がその朝の公用途中でいつものように瞬時の安らぎを求めて、一本のたばこに自由への憧れを燃やしていたとすれば、おそらく、そのままこの世から霧となって消えてしまっていたことはまちがいないところだった。爆裂一五分前には、私は爆心地の近くを自転車で走っていたのだから。
雲一つない晴天が暗くなる
次々に兵隊が埃をかぶってとび出してきた。どれもこれも魂を吹き飛ばされたような、それでいて、何かを真剣に求めているような名状し難い顔だった。私も一瞬呆然として、思わず、すぐ近くの土手にかけ上った。辺りは暗くなっていた。今の今まで、雲一つないまでに晴れ上がっていた青空が、物凄い爆裂音とともに赤黄色い閃光に塗りつぶされたと思った瞬間、空は黒煙ですっかり暗くなってしまったのだ。昼と夜のスイッチが、あっという間に切り替えられた感じだ。(何だ? 何だ?)、みんなのおびえた眼がしきりに問いかけている。
暗い市中のあちこちからメラメラ、メラメラと紅蓮の炎が舞い上がってきたのは、それからものの五分も経っていなかっただろう。 とにかく、何かすごい異変が起きたことだけはまちがいない。しかし、それがいったい何であるかは、もちろん誰にも分らなかった。
やがて、部隊は上を下への大騒ぎとなった。我々は、とび散った暗号書の拾い集めに、ひとしきり大わらわの態だった。死者が一人、二人と伝えられてくる。各兵舎は全部倒壊したという。やがて、(全員集合)の伝令がとんできた。 どす黒い顔をした兵隊が眼を光らせて走る。遮へい物の無い場所にいたために、閃光で露出部をやられたのだ。全く異様な感じである。早速救助その他の配置につく。
黒煙はやや薄らいだが、気味悪い大きな炎が全市を覆ってしまった。バリバリ、バリバリ、家屋の焼け落ちる音が物凄い。
比治山公園を埋める数千の半死の市民
「あっ!」、私は、ぞっとして息をのんだ。このさして高くもない丘である比治山さして、ふらふらと倒れかかる身体を、やっと支えながら上ってくる人々の群れ、群れ、しかもその人々のなんという異様な形相。私はあまりのことに思わず身震いした。
ほとんどすべてが衣類を着けていない。裸だ。一糸もまとわぬ者。パンツだけといえばまだいいが、それも、ぼろぼろに焼けて、申しわけに腰の紐に幾すじかの布切れがぶら下がっているにすぎないのだ。それどころではない。髪はすっかり焼けとんで丸坊主、眉毛さえ無い。それにもちろん素足だ。これだけで済んでいる者はまだましなのだ。眼がつぶれている。まぶたは鶏卵を入れたくらいの大きさにふくれ上がっている。視力は全く無い。それに唇はむくれ上がって、まるでコッペパンのようだ。いやそればかりではない。二十センチから三十センチくらいの細い布切れに似たものが幾すじとなく、手から足から垂れ下がっているのだ。私は、はじめ、それが何であるか見当もつかなかった。それは裂けた皮膚だったのである。
やがて、それらの人々がこの比治山の木々の陰を求めて、くず折れるようにばたばた倒れていく。黒煙はもうおおかた消えてしまった。灼けつく太陽が、あまりの暴虐ぶりに限りない憤りを投げつけんばかりに、ジリジリ照りつけてきた。暑い。息もつまりそうだ。
千人、二千人、こうした異形の群れはなおも続く。
「水! 水!」一様に水を求めて必死の呻き声。
いつの間にか、比治山公園はこれらの人々でうずまり、一歩の足もさし入れる余地さえないまでになってしまった。
いったい、何千人くらいの人々だっただろうか。もう木の陰、草の陰さえ無いのだ。水を打てば、じゅんと音をたてんばかりに焼けついた小石だらけの地面に、水蜜桃の皮をむいたような焼けただれた身体を、じかに横たえざるを得なかったこれらの人々の苦しさは、想像を絶するものがある。 「お母ちゃーん、お母ちゃーん」。泣き叫びながら、人波を分けて、母親を探して駆けずる子供。反対に、身も世もなく、我が子の名を呼びつづけておろおろしている母親。
「兵隊さん、眼が見えないよう」とすがりついてくる小学生の女の子。
「兵隊さん、こどもを助けて――」と、手を合せて、狂わんばかりにとりすがる母親。つい目のさきの燃えている家の中に、こどもがいる。木に足を挟まれて、どうしても引っぱり出せなかった。もう一人のこどもも助けなきゃならなかったし、ということだが声がふるえて、ほとんど言葉にはならない。火勢は猛烈を極めている。だめだ。どうにもならない。私は胸のつまる思いで、その母親が一心に指さす方を、黙って見つめるしかなかった。
「兵隊さん、この仇を必ず討って下さい」。苦しさの中で、歯をくいしばり、こぶしを突き出して、全身で訴える裸の男の人。 「気分がわるい、気分がわるい」と言いながら、抱き合って、じーっとうずくまっている五、六人の女生徒。
この山に避難してきた他部隊の兵隊であろう、二、三十人がさすがに声も立てず、座ったままうつむいて苦しさに堪えている。顔や手は焼けただれ、皮膚が裂けてぶら下がっている。頭髪は、戦闘帽に隠れていた部分だけが残り、露出部はきれいに剃り落としたようになっている。何という惨状、何という恐怖、これがこの世の地獄とでもいうのか。
やがて、黒い死の影が、この人たちにつぎつぎとおとずれてきた。薬は? 治療方法は? 何もない。何もできないのだ。
私は、もう動く気力もなくなった。むなしさが大きく拡がっていく思いだ。瀕死の苦しみにあえぐこれらの人々の間にすき間を見つけて、どっかりと坐りこんでしまった。(どうにでもなれ)、ふてぶてしい気持ちが私を支配しだした。人間、恐怖と悲哀の極限に立つと、平常神経が麻痺してしまうのかもしれない。
ここで、一つ書き加えておきたいことがある。私が坐り込んだすぐそばに、じっと、うずくまっている若い女の人がいた。見たところ、なんの外傷もなかったので、不思議に思って声をかけた。(外傷がみられない人は他にもいたが)。丸山定夫劇団の団員とのことだった。どんなにして、この比治山に逃れてきたのか、丸山定夫さんはじめ他の団員の人たちはどうだったのか。今にしてみれば、聞いておけばよかったと思うが、そんな話なんかしている状況でなかったことは言うまでもない。そして、この若い女の団員さんの比治山の後のことももちろん知る由もない。
瀕死の蟻の行列
「今から患者を似の島の病院へ運ぶ」という命令が出た。
「みなさん、似の島の病院へ行きますから、この山を降りて下さい」
ぞろぞろと、ふらつく足をやっと踏みしめながら、患者は山を降りだした。この人々が登ってきたのとは反対の、幅一メートルほどの急斜面の道とは名ばかりの山道である。
一列になって、よろよろと降りてゆく人々の群れ。千人、二千人、まるで瀕死の蟻の行列だ。上から見ていると、この列の中からあちらに一人、こちらに二人と倒れていく人の姿が見える。前の人の腰にすがりつくようにつかまっている人もいる。眼が見えないのであろう。かすかな呻き声だけが聞こえてくる。
私たちは、動けない重症者を担架で運ぶことになった。しかし、一人運ぶのに二十分はかかる。しかも僅かな数の担架である。それに、皮膚がぞろっとむけてすべるため、担架に乗せるのさえ一苦労なのだ。
山を覆う死体
なん回かの担架運びをすませて、ちょっと一息ついた時のことだった。足もとの路の傍らに瀕死の母親が倒れていた。もう動くこともできないのだ。おそらく、眼も見えなくなっていたろう。まだよちよちの幼児が、その母親の乳房に顔をつけて、しきりに水をねだっている。「坊や、いい子だから我慢するんだよ」、私はこう言うよりほかになかった。すると、身動き一つしなかったこの母親は、坊やの頭に手をかけたまま、「坊やいい子だから我慢して」と、虫の声でなだめるのだ。(この母親は間もなく死んでいく。そして、この子はいったいどうなるんだろう)私は眼頭が思わず熱くなったことを、今でも忘れることができない。
何処からか回されて来たのか、トラックが二、三台やって来て、散乱している屍体を、まるで荷物でも扱うように放りこんでは何処かへ運んでいく。
地上でどんな異変が起きようと、天地の運行は一分の狂いもなく回転する。太陽が、いつのまにか西に傾きかけた。心地よい夏の夕風といいたいところだが、何万という屍体の上を吹き渡ってきた風は、吐き気を催す臭いを頭の芯まで吹きつける。
全市を覆って、ますます勢いを増してゆく火は、一段と赤味を加えて、気味悪い地獄の炎を思わせる。
恐ろしい火熱と風圧の跡
はじめは気付かなかったが、爆心地から直線距離二キロのこの比治山の木、葉もろとも、ほとんど赤茶けている。火熱に焦げたのだ。地面は、吹きとばされた木の葉でいっぱいだ。どんなに激しい暴風でもこんなにはなるまい。高圧線の鉄柱が、グンと六十度くらいにねじ曲がっている。なんという強烈な火熱と風圧。
遮へい物の無い所にいた者が吹きとばされたのも当然である。さらに、私たちを驚かせたのは、営庭(ちょっとした広場程度のものだったが)に立っていた黒い馬が、火熱を受けた側だけべろべろに焼けただれて反対側は普通と少しも変わらなかったことだ。
やがて文字どうり死の夜がやってきた。非常警備につく。動哨だ。
無数の死霊の啾々たる哭声に全身を取り巻かれている思いがする。
「ううう・・・」というかすかな呻き声が、あちらの草蔭、こちらの木蔭から、闇を通してまつわってくる。耳を覆いたい気持ちで歩いていると、なにか柔らかい、重ったるいものにつまずいて、ハッとする。屍体だ。じーんとくる、それを振り切るように見上げる闇の中に、めらめら、めらめらと地獄が燃えつづけている。
一夜が明けた。八月七日。飯はだれもがちょっと箸をつけただけだ。食欲などあるはずがない。たいていの者は、昨日の大変事は、とにかく物凄い爆弾であったことはまちがいないとは思っていた。しかし、それが、原子力による爆弾だなどとは、もちろん知るはずもなかった。
営舎の片付けが始まる。黙々と作業が続けられる。壊れた電報班の兵舎の上に、一抱えは十分ある松の木が根を上げて倒れている。
四、五日後の夜の街で
爆発があって四、五日が怱々のうちに過ぎた。あらかた屍体は片付いたが、患者はどこの病院でもばたばたと死んでいっているという話が伝わってくる。
異変以来初めての公用命令が出る。しかも、時刻は午後十一時を過ぎている。宇品まで、徒歩で、ただ一人で行くのである。
焼けても曲がらないのは道路だけか。その道が、闇の中にうっすらと白く光っている。こつ、こつ、こつ、聞こえるのは、私の兵隊靴の踵の音だけである。
死の街、まさに文字どうりの死の街だ。焼野が原が、闇の中に無限に拡がっているのだ。思い出したように残り火が、ちょろちょろ、と暗闇をなめる。すえた屍臭が鼻をつく。
生きとし生けるものすべてが姿を消した死の世界とは、こういうものではなかろうか。鬼気迫る死の静寂の中で、ぞーっとする寒気が全身を走る。突然、遠くの闇の中から、「へいたいさーん、たすけてー」という弱いが、必死にすがりつこうとするような女の人の声が、私の足に巻きついてきた。私の靴の音が響いたのだ。
私は思わず、耳をふさぎたい気持ちで小走りになった。その私の後ろから、しぼり出すような声が、なおも追いかけてくる。青白い残り火が、また、ちょろちょろと燃え上がって、すーっと消えた。
生き残った者の惨めさ
それからまた幾日か過ぎた。やがて、昼間には、僅かだが道行く人の姿が見られるようになった。十四、五センチほどの小さなうなぎの子を、びんの中に入れて、家に帰る途中の十才くらいの男の子に出会った。「川で採ってきたの。お母さんは、あの時から夜になると、こわい、こわいと言って、暴れ出すんだよ。今、寝てるけど、このうなぎ、お母さんに食べさせてやるんだ」。無邪気に話していたが、さびしそうな顔だった。
知り合いのお婆さんたちなのだろう。路上で抱き合ったまま、おいおい泣いている。なにかの偶然から、お婆さんたちだけが助かり、子どもや孫は死んでしまったのかもしれない。
言葉では言いつくせない恐怖、苦痛のあとだけに、生き残った家族たちの一層の悲しさ、惨めさは、どんなに大きかったことか。また、どんなに多くの悲涙の情景が、荒涼たるこの焼野が原に繰り拡げられたことか。
(おわり)
あとがき
季刊誌掲載後、再度若干、削除補筆した。
これが、私の広島被爆体験の最終的なメモということになる。