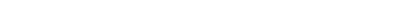書斎
体温 ── SIDE H ──
ネオンの光がぎらつく中、そこだけが薄暗い闇に包まれていた。
女だと思った。
俺が見つけた時、そいつは夜の繁華街の片隅で、コートも着ずに店の軒先に座り込んでいた。もう12月も中旬冬真っ只中だというのに、全く正気の沙汰じゃない。
長い黒髪を後ろで無造作に束ね、スラックスとシャツという簡素な出で立ち。化粧っ気もないのに白い頬と薄く紅を刷いたような唇。手に何か持っているようだったが、それ以上は判断がつかなかった。縮こまるように丸められた肩はとても細く、華奢だ。
連れらしき人物がいないことを確認した俺は、隣にしゃがみこんで声をかけた。言うまでもなくナンパ目的だ。
ぼんやりと行き交う人を眺めていた視線が、やっと意思を持って俺に向けられる。
──その瞳は何だか飢えているように見えた。
†
「いや、参ったな。まさか男だとは思わなかった」
「…そうですか?」
「だって髪長いし身体細いし」
「…そうですか」
目の前に並んだファーストフードには手をつけようとせず、そいつは淡々とした声で答えた。少々気まずい空気。
恥かしい話だが、立ち上がらせるまで俺はそいつが男だとは予想すらしていなかった。立ち上がらせて初めて、女性一般の平均より確実に高い身長と哀れなほど薄い胸に気づいたんだ。男をナンパしてしまったと理解するまでの約数秒間、黙って見詰め合っていた俺たちははたから見たらマヌケだったに違いない。女性らしい細い線ではなく、不健康一歩手前まで痩せた正真正銘の男だったわけだ。俺の目も大分ガタがきているようだ。
当然ナンパは中止、俺は性別を間違えた非礼を詫びて立ち去るはずだった。そう、立ち去るはずだったんだ。それなのに気が付けばそいつ──『ユウ』と言うらしい──と二人で手近なファーストフード店に入っていた。自分でも何故だかわからない。
──こいつのために何かしてやらなければ。
何の根拠もない欲求。立たせようと掴んだ手が異様なまでに冷え切っていたせいかもしれない。例えるなら……このまま置いておけば死んでしまうのではないか? そんな冷たさ。
あまりにも寒そうだったから同情してしまったんだ、他意はない、いくら女顔だとはいえ男をナンパする趣味は持ち合わせていないぞ、と何度も自分に言い聞かせる。
ユウが手にもっていたのは何故か白衣だった。白衣を着ているところを想像した俺は、まるで死に装束のようだなと思い、それから慌ててその考えを頭から振り払う。何を縁起でもないことを。相手にも失礼だろう。
「食わねぇの?」
相変わらずユウは黙り込んだままロクに返事もしない。俺はわざとらしく溜息をついてみせた。
「コートも着ないで外にいたから身体冷えてるんだろ? 食えば少しは暖まるぜ?」
ユウは俺の言葉にしぶしぶ食事に手をつけた。何もそこまで嫌そうに食べなくてもいいのに。
「もしかしてこういうの嫌いとか?」
こうも嫌々食べられると何か無理矢理押し付けているようでばつが悪い。不健康そうだし、今ハヤリの『食物アレルギー』とかそんなヤツなんだろうか?
俺のそんな心配を読み取ったのか、ユウは困ったように目を伏せた。
「嫌いというわけでは。食欲がないだけです…」
「そう? 腹減ってるように見えるけど?」
口に出してみてああそうだった、と俺は思い出した。こいつを食事に誘ったのはこのせいもあったんだった。寒そうにも見えたが、それ以上に飢えた空気を身にまとっていたから。だから何か食べさせてやろうと無理矢理店に連れてきたんだ。
だが俺の言葉を聞いた瞬間、ユウは表情を歪ませた。本当に瞬きする間ほどの変化。おや、と思って見直した時にはもう無表情に近い状態に戻っている。
「……気のせいですよ」
微かに嫌悪感のこもった口調。
「ユウってどんな字?」
ますます悪化した雰囲気を取り繕うように尋ねた俺に、ユウは妙に苦労しつつ口の中のものを飲み込んでからこちらを見た。
「ユウキュウのユウです」
「ユウキュウ?」
とりあえず頭の中で漢字変換を試みる。
「有給休暇とかの有?」
ユウは俺の言葉に小さくかぶりを振ると、少し考えてから
「ユウユウジテキのユウ」
と答えた。
「ごめん、わかんねぇや。何か書く物ない? 鉛筆でもボールペンでもいいけど。紙はこれで──」
どちらの説明でも漢字を思い浮かべることができなかった俺は、紙ナプキンを一枚とってユウに差し出した。しかしユウは受け取ろうとはせず、ただ冷えた視線をこちらに向けている。
「わからなくても、別に困りませんよ」
こんな字もわからないのか、と言われているようでむっとした俺の胸の内に気づいたのだろうか。ユウは取り繕うように付け足した。
「漢字は記号に過ぎません。音として呼ぶことができればそれでいい。友人の名前を呼ぶときいちいち頭の中で漢字を思い浮かべますか?」
はぐらかされているな、とわかっても上手く反論する言葉が見つからない。
「そりゃまあ確かに呼ぶ分には漢字が表示されるわけじゃないし?」
ロールプレイングゲームや漫画のようにふきだしが出てそこに台詞が並んだら面白いけどなぁと頭の片隅で馬鹿なことを考え、その一方で苛立ちを押さえ切れず俺は頭を掻いた。酷くもどかしい。
「ユウ、はこう書くのかもしれない、こうかもしれない…」
蒼白く細い指がテーブルの表面で次々といくつかの漢字を綴るような動きをする。残念ながらその中に『ユウユウジテキのユウ』があったかどうかはわからなかった。
「しかしどの字を使ったとしても、貴方が口に乗せるのは『ユウ』という音に変わりはありません」
それからユウは少し間を置き、唇の端だけ持ち上げるような笑みを浮かべる。
「……それに、もしかしたら英語の『You』かもしれませんよ」
†
店員の視線が痛くなってきたところで、俺はユウを連れて冷たい風の吹く街の中へ戻った。店内で粘れる時間には限りがあるものだ。
あの後「どうみたって日本人だろ」とツッコミを入れてやると、ユウは何故かとても嬉しそうに笑って「日本人に見えますか?」と尋ねてきた。そのまま笑い続けているのを見てさすがに不安になる。いくら俺の目が節穴になっているとはいえ、ここまで流暢に日本語を使いこなして、漢字の薀蓄まで語ってくれたこいつが外国人だとは思えない。
痺れを切らして「日本人じゃないのか?」と聞くと「ありがとう」と何故か礼を言われてしまった。まったくおかしなヤツだ。
だが、そのやり取りのおかげか、ユウは少し俺に心を開いてくれたようだった。時折だが軽口らしきものも言ってくれる。
「コート無いってのは痛いよな。この時間じゃ店はしまってるし……寒いだろ?」
「別に」
そっぽを向いたユウの頬に、手の甲で軽く触れてみる。やはり冷たい。
「嘘つけ。まだこんなに冷えてるじゃねぇか」
「冷え性なんですよ」
「さよか」
真面目に応える気はないらしい。
「で、その白衣は何? 仕事か何かで使ってるのか? いや、言いたいのはそんなことじゃなくて。それ一枚だけでも羽織ったら? ないよりマシだろ?」
「変に注目されるから脱いだんです。街中ではもう着ません」
こんな繁華街の中を白衣を着ている人間が歩いていたら誰だって不審に思うに決まっている。好意的に見たって酔っ払い相手の薬局の店員くらいしか思いつかないし、好き好んで寒風吹きすさぶ中仕事着のまま出歩く店員はいないだろう。
「ナンパした可愛い女の子相手なら、俺だって格好つけてコートの一枚くらい貸すけどよ。野郎相手には貸さねぇぜ?」
「貸してくれなんて言っていませんって」
「それは何かい? コートの要らない暖かい場所に連れて行けってこと? ユウが女だったら──」
その辺のホテルにでも連れ込んでやるけど、と言いかけてやめる。そういう冗談が通じるタイプには見えなかったから──いや違う、半分くらいは本気でそう思ってしまったから慌てて言葉を飲み込んだんだ。そもそも女だと思ってナンパしようとした俺だったし、未だにどこか男だと信じられない部分もある。
「僕が女だったら?」
そんな俺の気持ちを知ってか知らずか、ユウは俺を振り返る。何度見てもやはり性別不明な容姿に変わりはない。何でこれで男なんだか。全く神様は根性曲がりだ。
「あぁ、ユウが女だったら俺の奢りで徹カラぐらい連れて行ってやろうかってとこだな。んで、朝まで歌いながら寒さしのぐ」
「……僕は寒くないですよ」
──意地っ張りめ。この温度で寒くなかったら人間じゃない。
そう思った俺は無言で自分のしていたマフラーを巻いてやった。不思議そうにこちらを見上げられ、少し照れくさいような何とも言えない気分に陥る。男相手なのが本当に悔しい。
「可愛い女の子じゃねぇから、マフラーで我慢しな。ほれ、手袋も持ってるから貸してやるよ。……?」
ユウの視線は差し出した手袋ではなく、マフラーを外して露わになった俺の首筋に注がれていた。
「何だよ?」
ゆっくりと手が持ち上がり俺の喉元に触れる。死人のように冷たい指。
「うわ冷てっ!」
反射的に首を竦めた俺に、ユウははっとしたよう手を引っ込め慌てて視線を逸らした。
「……ごめんなさい」
何に対して謝られたのか咄嗟に理解できなかった俺に、ユウは口篭もりながら
「……寒いでしょう……?」
と続けた。
それまでの感情の読み取りにくい口調ではなく、はっきりと不安そうな響きを宿した声。
本気で俺の心配をしてくれているらしい、そう思うと自然と笑みが零れた。ガードの固い女を口説いていて、少し手ごたえがあったときの気分に似ている。相手が男だって心を開いてもらえれば嬉しい。
「そっちほどじゃないさ。このぐらい平気だって」
「貴方が平気でも僕が平気じゃないんです……」
ユウは視線を落とし、じっとアスファルトを見つめている。
「そんな気にするなよ。何だかこっちが悪いことしてるみたいじゃねぇか」
返答がない。
「ユウ?」
アスファルトを見つめたまま動かないユウ。
「おい、ユウってば!」
その肩に置こうとした俺の手は、ユウが唐突にしゃがみこんだせいで虚しく空気を掴んだ。不審に思いつつ、俺も腰を落とし顔を覗き込む。
「どうかした?」
のろのろとこちらを向いたユウの唇が小さく動く。
「何? 聞こえないって」
「……ぃ……」
ギリ、と爪の痕がつくほど強くユウは自分の喉を掻いた。慌ててその手を掴んで止めさせる。吸い付くようにひんやりした肌。
「何やってんだよ!? どうしたんだ!?」
「……気持ち……悪い」
「へ?」
簡潔かつ明瞭。言われてみれば元々良くない顔色がますます悪化しているようにも見えた。
「苦し……」
そのままぐらっと傾いだユウの身体を慌てて抱き止める。
「……か……て……」
喘ぐように洩れる掠れた声はほとんど聞き取れなかった。
「とりあえず救急車……」
持病の発作か何かだろうか? それなら放ってはおけない。
119番通報しようと懐からケータイを取り出した俺の手首をユウが掴んだ。相変わらず冷たい手。
触れられた瞬間背筋に悪寒が走った。この冷たさは異常だ、と俺の脳裏で警鐘がなる。本能的な恐怖。何故俺はこいつの相手をしているんだろう?
何かに蝕まれていくような錯覚。締め付けてくるその力は病人のものとは思えない。そのあまりの冷たさにこちらの体温まで奪われていきそうな──
「いらな…い…呼ばな……いで……」
反射的にその手を振り払おうとしたのとほぼ同時。ユウの必死な声が耳に届き、俺はハッと動きを止めユウを見た。見てしまった。
ユウの視線が俺を思考を停止させる。
そうだ、病人を振り払おうとするなんてどうかしてる。俺が今しなければならないのは、こいつを助けることだ。何故ユウを怖いだなんて思ったんだろう? 必要以上に手が冷たいのはきっと体調が悪いからで、何も怖がるようなことじゃない。急に掴まれて少し驚いただけだ。そうに違いない。
「少し我慢してくれよ」
素早く周囲を見渡し、俺はユウを抱き上げた。
何が原因かはわからないが、とにかくこのままではいけない。休める場所に移動しようと、俺はユウを抱いたまま歩き始める。
病的なまでに蒼白い顔色の中で唇だけが真っ赤に際立って見えた。
「っとに大丈夫かよ…?」
選んだのは近くにあったホテルだった。男と二人連れで入るのは少々不本意だが、ユウは病院には行きたくないと言い張ったし、騒音喧しいカラオケBOXに入るわけにもいかないだろう、と自分を納得させる。
「まだ気持ち悪い?」
結局ユウは食べたものを全部吐いた。無理矢理食べさせた俺が原因かと思うと気が重い。罪悪感。バスルームで背中を撫でてやりながら、ぐったりとしているユウにひたすら謝るしかなかった。
弱々しくかぶりを振ってユウが立ち上がる──立ち上がりかけてよろめいた。
「馬鹿! 調子悪いやつは大人しくするんだよ!」
間一髪で受け止めて、そのまま担いで部屋に戻ると、有無を言わさずベッドに寝かせる。
「あ……」
落ち着き無く視線を泳がせているユウに、俺は軽く肩を竦めて見せた。
「安心しろ、襲ったりしねぇから。ゆっくり休めよ」
返事は無いが微かに頷いたように見えたので、ユウに背を向けてベッドの端に腰をおろす。女相手だったらこれ程おいしいシチュエーションはないだろうに、俺はどこで何を間違えたんだろう。
そして、一服しようかとタバコを取り出したその時。
いつ起き上がったのか、いつ忍び寄ったのか、ユウの腕が背後から俺の身体にまわされた。
「ユウ?」
ユウは答えず無言で俺を抱き締めてくる。
「おいおい、何の冗談だよ? 女だったら大歓迎だけど……」
柄にも無く焦って馬鹿なことを口走っていると、耳元に冷たい吐息がかかった。
……冷たい?
「──!?」
何が起こったのか解からなかった。首筋に鈍い痛み。逃げようとしても身体にまわされた腕は外れない。今にも折れそうな華奢な腕なのに、信じられない程の怪力。
辛うじて視線をめぐらせると、そこには血のように真っ赤に染まった1対の瞳。
──その瞳は何だか飢えているように見えた。
初めにユウの目を見た時に俺が覚えた感想は間違っていなかった。本当にユウは飢えていたんだ……。